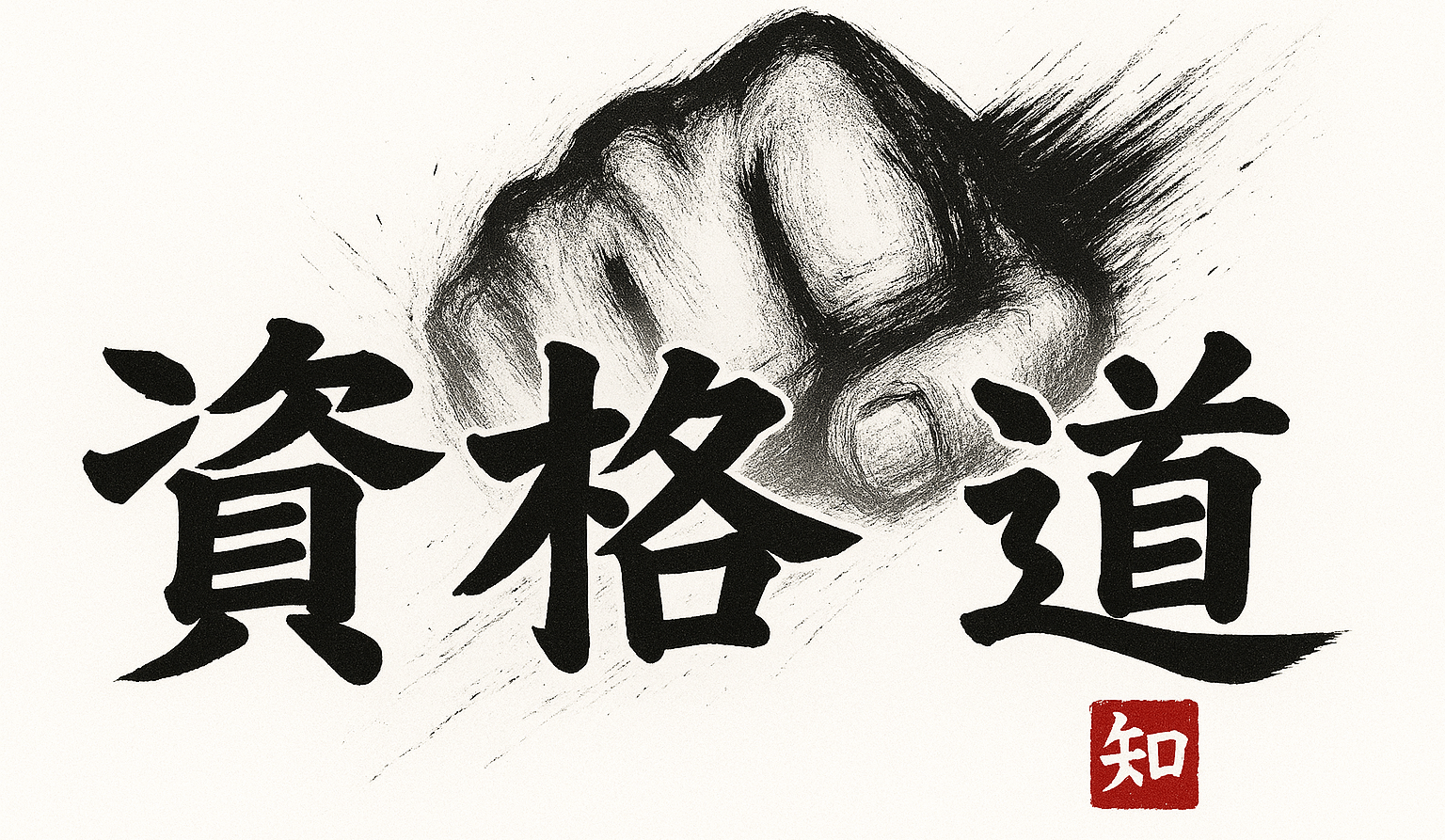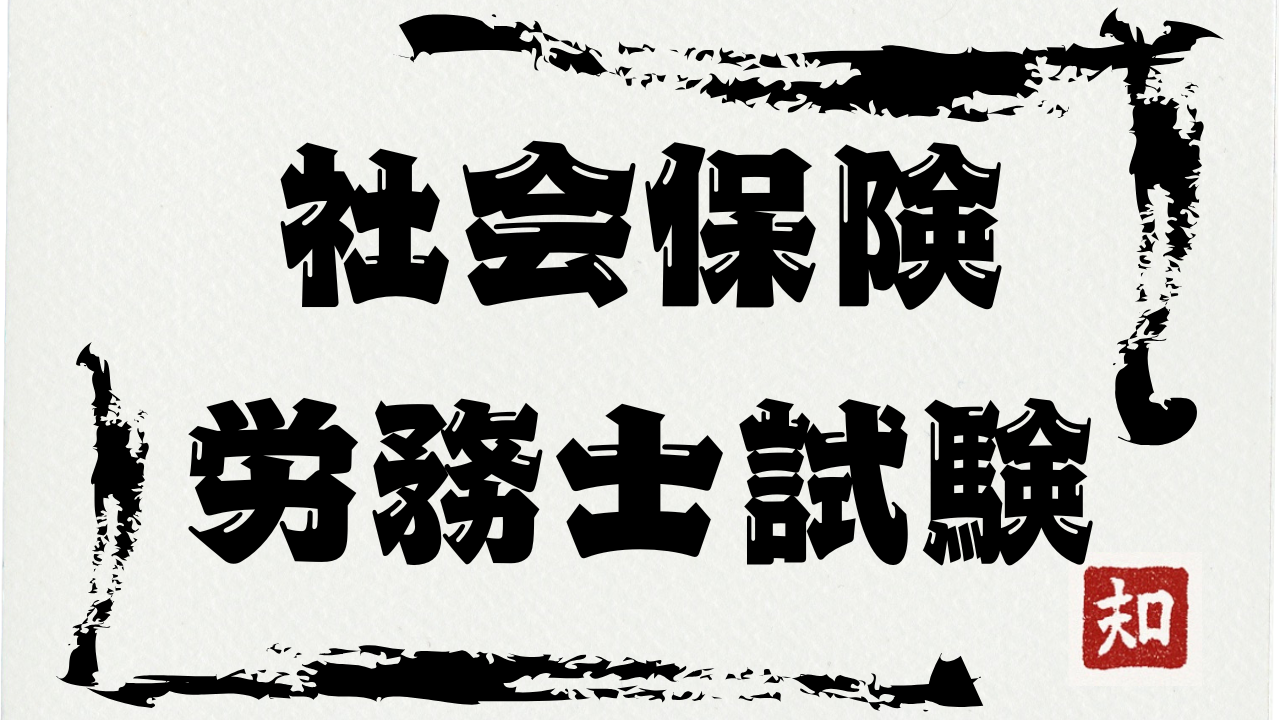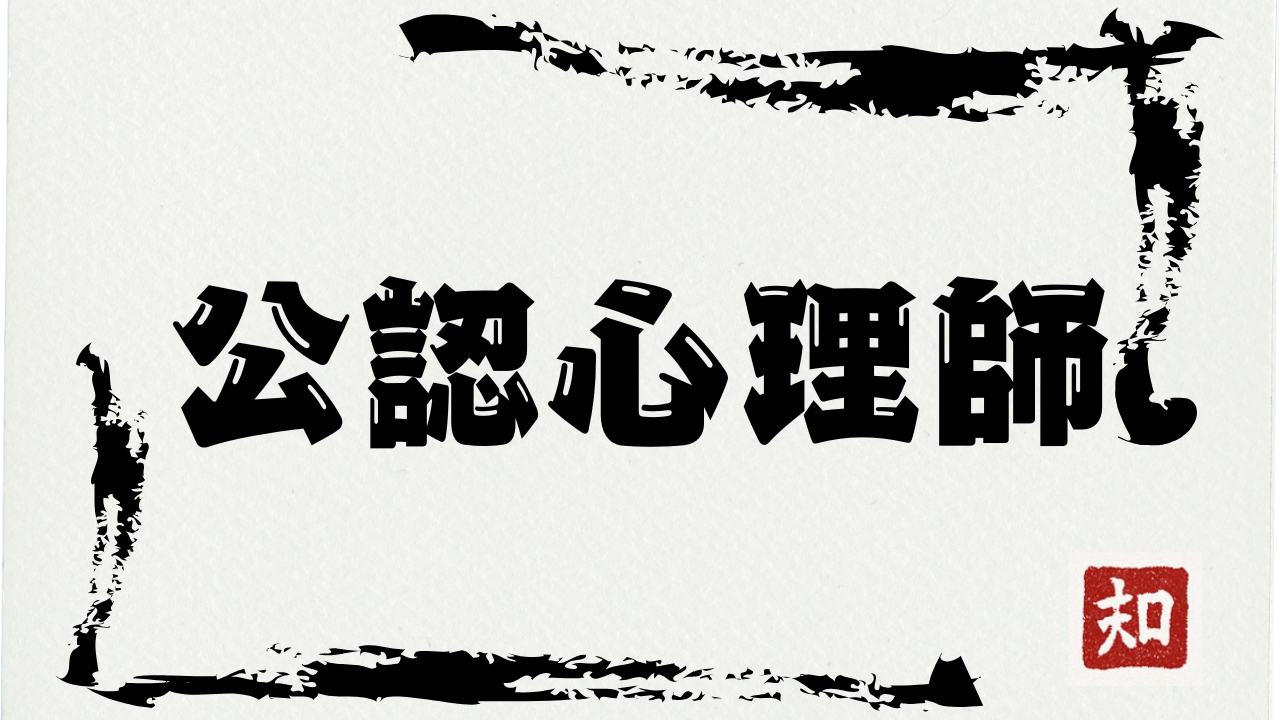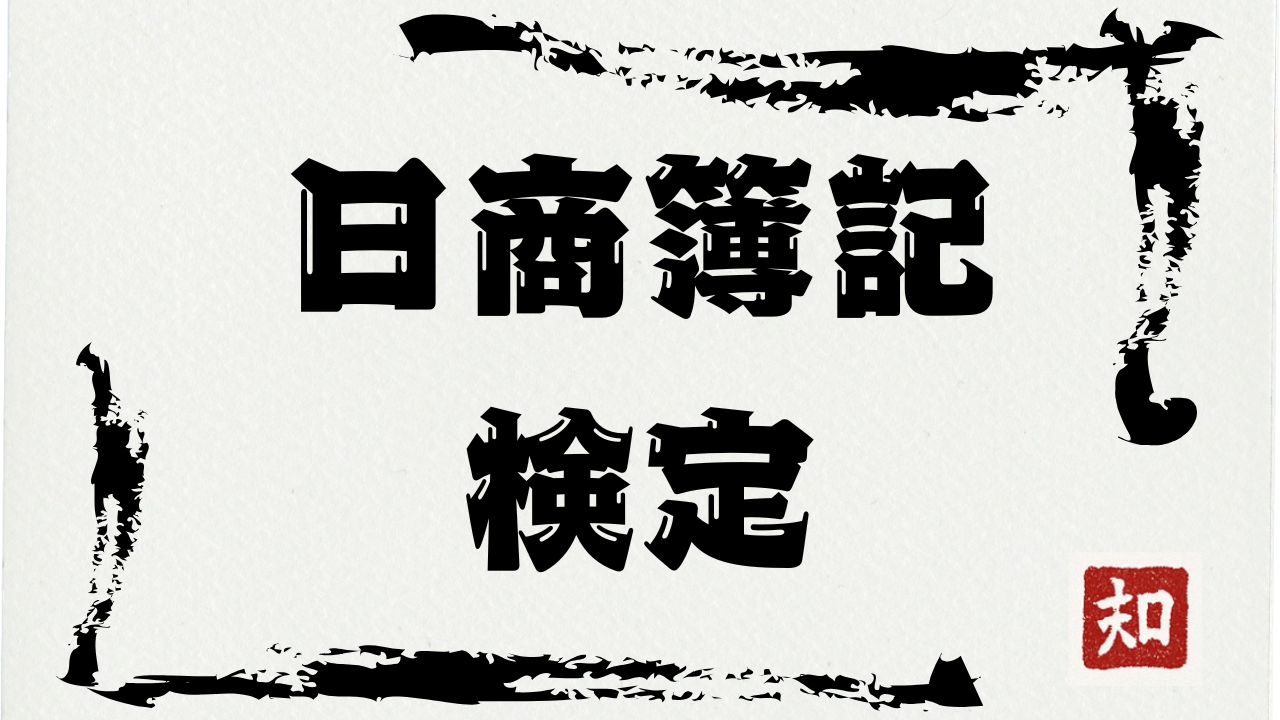概要
社会保険労務士試験は、年金・社会保険・労働基準法など幅広い労務管理の専門知識を問う国家資格試験です。
毎年1回、8月下旬に全国規模で実施されます。
この試験は合格率6〜8%前後の難関資格ですが、合格すれば社会保険・労務の専門家として、企業や社労士事務所等で活躍できます。
試験内容
受験資格
以下の3つのうち、いずれかの受験資格を満たす必要があります。
1. 学歴による受験資格
以下のいずれかに該当することが必要です。
- 大学、短期大学、専門職大学、専門職短期大学、高等専門学校(5年制)卒業または専門職大学の前期課程修了(専攻は不問)
- 大学(短期大学除く)で62単位以上の卒業要件単位を修得
- 専修学校専門課程(修業年限2年以上、授業時間1,700時間以上)修了
- 厚生労働大臣が認定した看護師や保育士養成施設などの学校卒業
- 全国社会保険労務士会連合会の審査で短期大学と同等以上と認められた者
2. 実務経験による受験資格
- 労働社会保険関連法令の実施事務に関わった法人の役員・従業者として通算3年以上
- 公務員等の行政事務に3年以上従事した者
- 社労士、弁護士の補助事務に3年以上従事した者
- 労働組合職員・役員や事業主で労務を担当した期間が3年以上
- 労働社会保険関連の事務に3年以上従事する職務経験者
3. 国家試験合格による受験資格
- 行政書士試験合格者
- 司法試験予備試験や旧司法試験第1次試験合格者
- 厚生労働大臣が認定した他の国家試験合格者(不動産鑑定士、弁理士、公認会計士など)
試験方式
- 「選択式試験」(文章穴埋め式)
- 「択一式試験」(五肢択一マークシート)
- 両方とも同日に全国一斉実施
出題範囲
出題範囲は、「労働関係科目」と「社会保険関係科目」の2領域・計8科目で構成され、択一式・選択式いずれの試験にも広い法知識が求められます。
労働関係科目
- 労働基準法及び労働安全衛生法
- 労働条件・労働時間・賃金・就業規則・安全衛生管理など
- 労働者災害補償保険法(労災保険)
- 業務災害・通勤災害の給付、障害・死亡・療養給付など
- 雇用保険法
- 失業給付、育児・介護休業給付、雇用安定助成、保険料徴収など
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律
- 労災・雇用保険料の徴収、納付、年度更新、過誤納還付など(*択一式のみ)
- 労務管理その他の労働に関する一般常識
- 労働契約法・男女雇用機会均等法・パート労働法・労働経済動向・労働統計等
社会保険関係科目
- 健康保険法
- 健康保険資格取得・給付・傷病手当・出産手当等
- 厚生年金保険法
- 年金の適用・給付内容・改定・障害・遺族年金等
- 国民年金法
- 被保険者資格、老齢年金、障害・遺族給付、保険料納付等
- 社会保険に関する一般常識
- 医療・年金・福祉政策、関連法規、社会保険制度の動向・統計等
出題数
- 選択式:上記8科目から各1問(合計8問/各5点)
- 択一式:労働関係6科目・社会保険関係2科目計7科目から各10問(合計70問/各1点)
※労働保険料徴収法のみ択一式で単独出題、選択式には含まれません
試験時間
- 選択式:80分(10:30~11:50)
- 択一式:210分(13:20~16:50)
合格基準
- 選択式:総得点で28点以上、かつ各科目3点以上
- 択一式:総得点49点以上、かつ各科目4点以上
- 年によって合格基準の調整・救済措置あり
合格率
約6~7%
受験料
15000円
受験会場
全国19都道府県(北海道・宮城・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・石川・静岡・愛知・京都・大阪・兵庫・岡山・広島・香川・福岡・熊本・沖縄)から選択可能
合格後
STEP1
合格通知の受取
- 合格発表後、合格証書や成績通知書が簡易書留で郵送されます。
- 記載内容の確認と大切な保管が必要。
STEP2
実務経験または事務指定講習
- 2年以上の労働社会保険諸法令の実務経験があれば直接登録可能。
- 実務経験がない場合は「事務指定講習」という約4ヶ月の講習(受講料約7万7,000円の通信+面接指導)を受講し修了する必要あり。
STEP3
全国社会保険労務士連合会への登録申請
- 必要書類を準備し申請。
- 書類審査後、問題なければ登録証の交付。
STEP4
都道府県社会保険労務士会への入会
- 連合会登録後、所属都道府県の社労士会に入会。
- 独占業務を行う資格の正式スタート。
STEP5
就職・開業開始
- 登録・入会後は「勤務社労士」や「開業社労士」として活動開始が可能。
- 研修や勉強・ネットワーキングを継続しながら実務経験を積む。