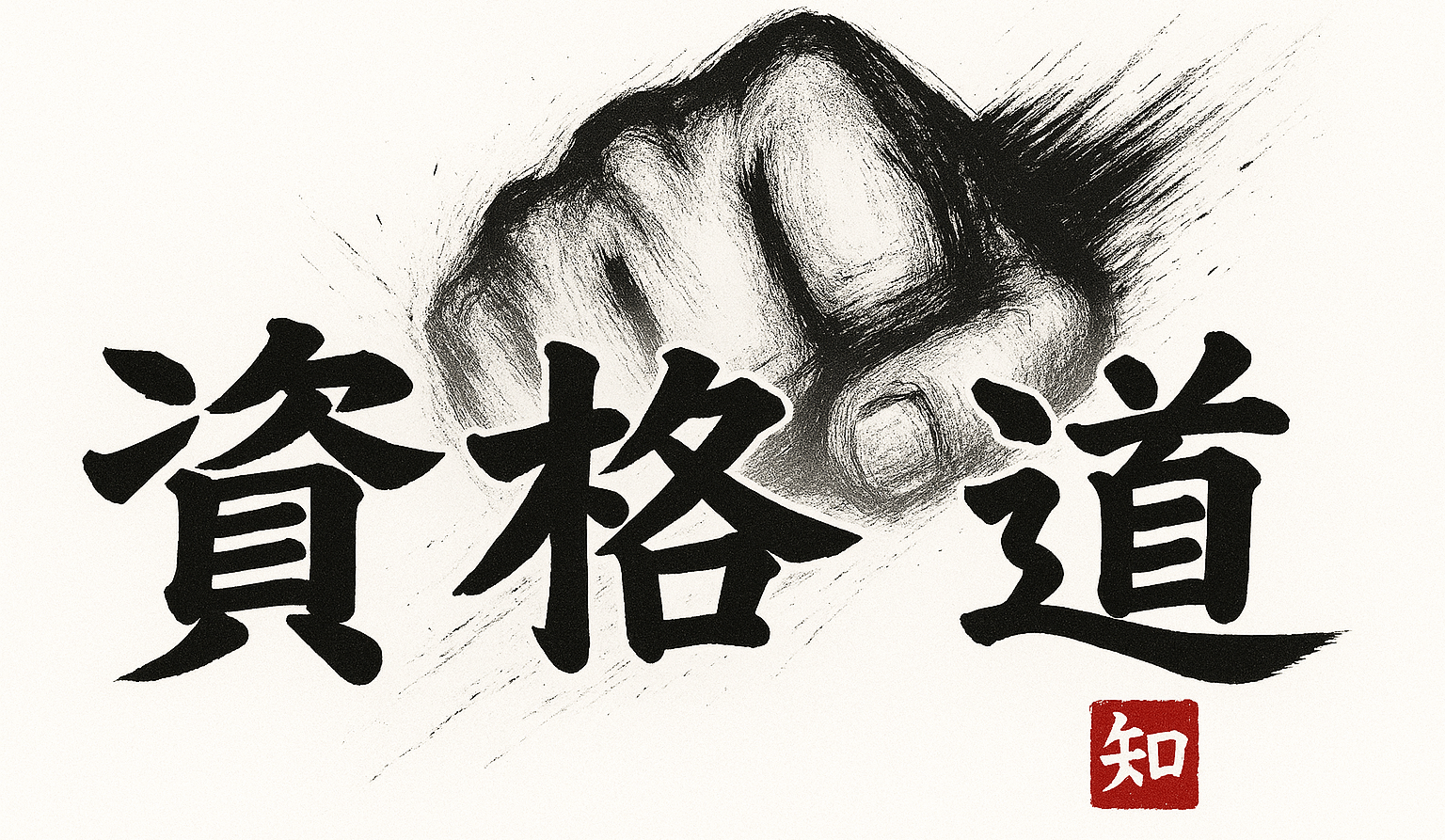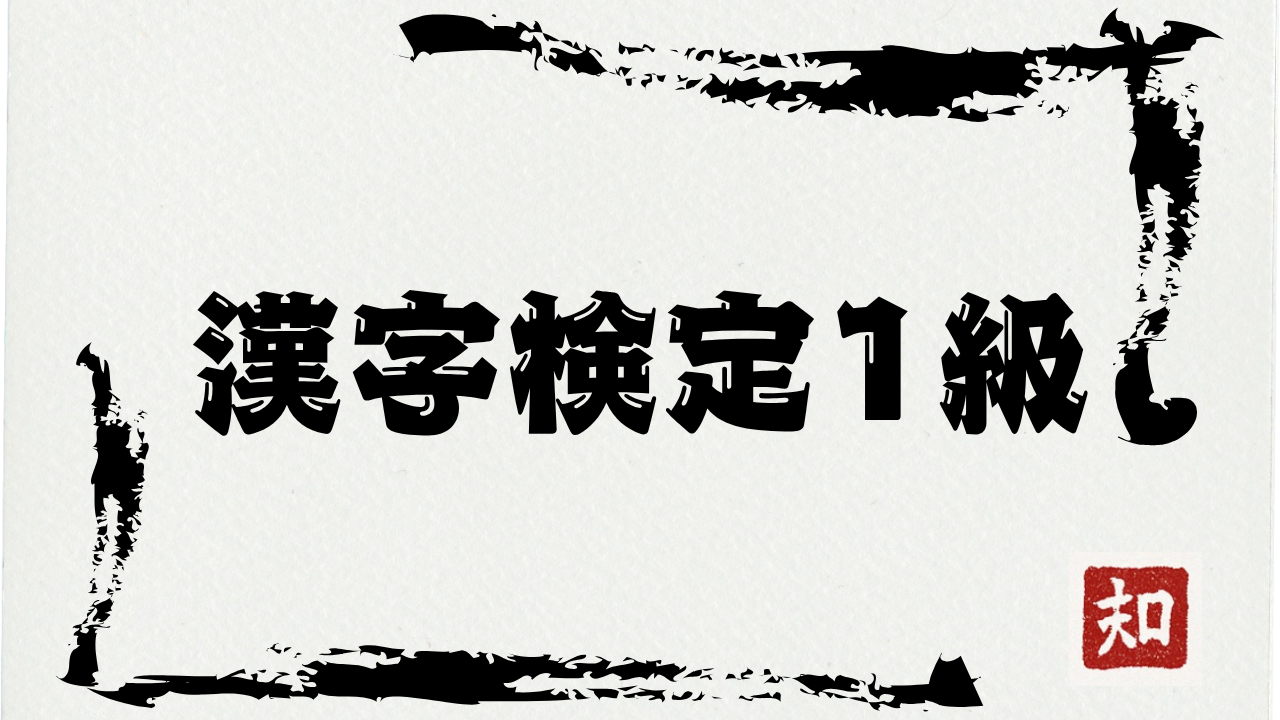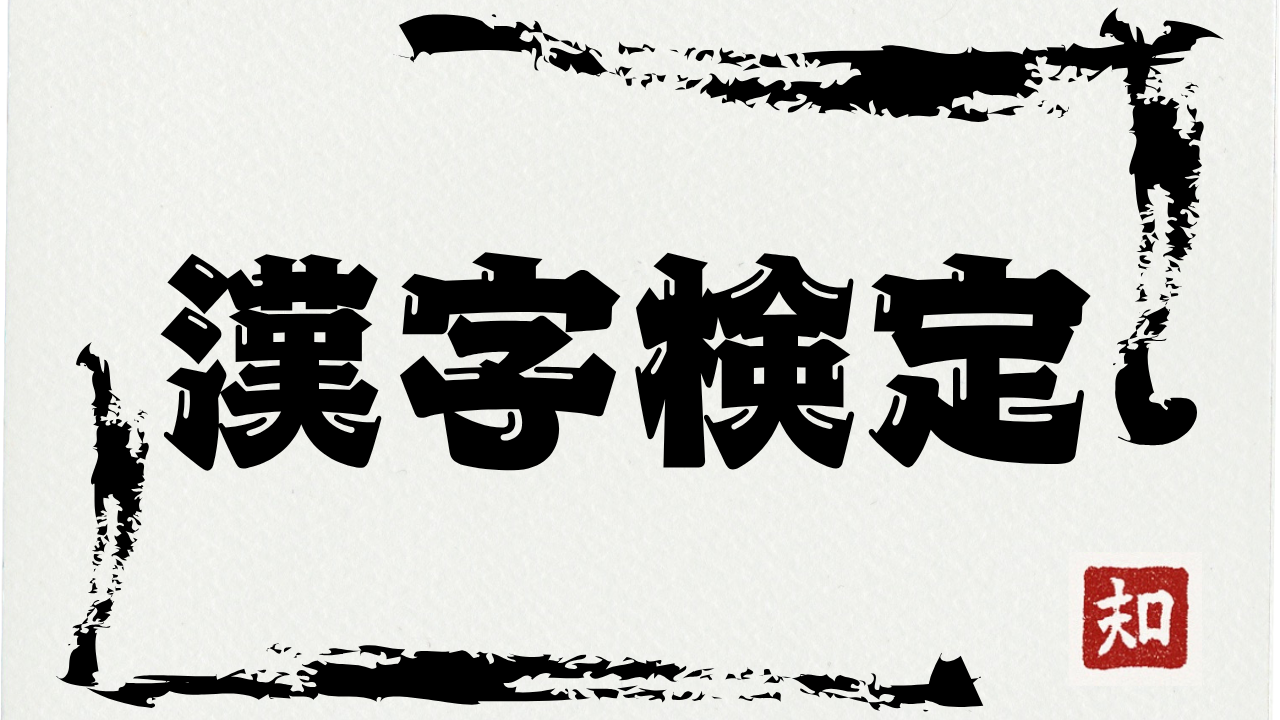概要
レベル
大学・一般程度
常用漢字を含めて、約6000字の漢字(JIS第一・第二水準を目安とする)の音・訓を理解し、文章の中で適切に使える。
出題内容
- 読み【30問✕1点】
- 短文中の傍線部の箇所の漢字の読みを答える問題。
- 30問中、20問が音読み、10問が訓読みで構成されている。
- 書き取り【20問✕2点】
- 短文中の傍線部の箇所のカタカナを漢字に直す問題。
- 音読み・訓読み合わせて16問、同音訓異字語が4問、国字が2問で構成されている。
- ※国字:漢字の形を真似て日本で作られた和製漢字のこと。
- 語選択書き取り【5問✕2点】
- 与えられた意味に適合する語を、左の四角の中のひらがなから選択し、そのひらがなを漢字に直す問題。
- 常用漢字外の漢字を含む熟語の意味を理解する必要がある。
- 四字熟語【10問✕2点+5問✕2点】
- 2つの小問に分かれている。
- 問1は、左の四角の中のひらがなで示された四字熟語の2文字分を選択し、ひらがなを漢字に直して四字熟語を完成させる問題。
- 問2は、与えられた意味に適合する四字熟語を左の四角の中から選択し、傍線部の箇所の漢字の読みを答える問題。
- 四字熟語の読み書きに加えて意味も理解する必要がある。
- 熟字訓・当て字【10問✕1点】
- 熟字訓や当て字の読みを答える問題。
- ※熟字訓:2文字以上の漢字で構成される熟語に、単語単位で訓読みを当てた読み方。
- ※当て字:漢字の意味に関係なく、音・訓を当てはめた語。
- 熟語の読み・一字訓読み【10問✕1点】
- 与えられてた熟語の読みと、その語義にふさわしい一字訓読みを答える問題。
- 当該漢字の音読みと訓読みを理解する必要がある。
- 対義語・類義語【10問✕2点】
- 与えられている熟語の対義語・類義語に相当する、左の四角の中のひらがなで示された熟語を選択し、漢字に直す問題。
- 対義語が5問、類義語が5問で構成されている。
- 故事・諺【10問✕2点】
- 故事・諺の中のカタカナを漢字に直す問題。
- 文章題【10問✕2点+10問✕1点】
- 明治・大正・昭和期などの著名な作家の文芸作品などの一部を題材に、文章中の漢字の読み書きを答える問題。
- 読みが10問、書き取りが10問で構成されている。
以上200点満点でで構成されている。
合否基準
80%程度
試験時間
60分
検定料
6000円
受験資格
特になし
試験会場
公開会場のみ
全国47都道府県の主要都市約150箇所に設けられている。